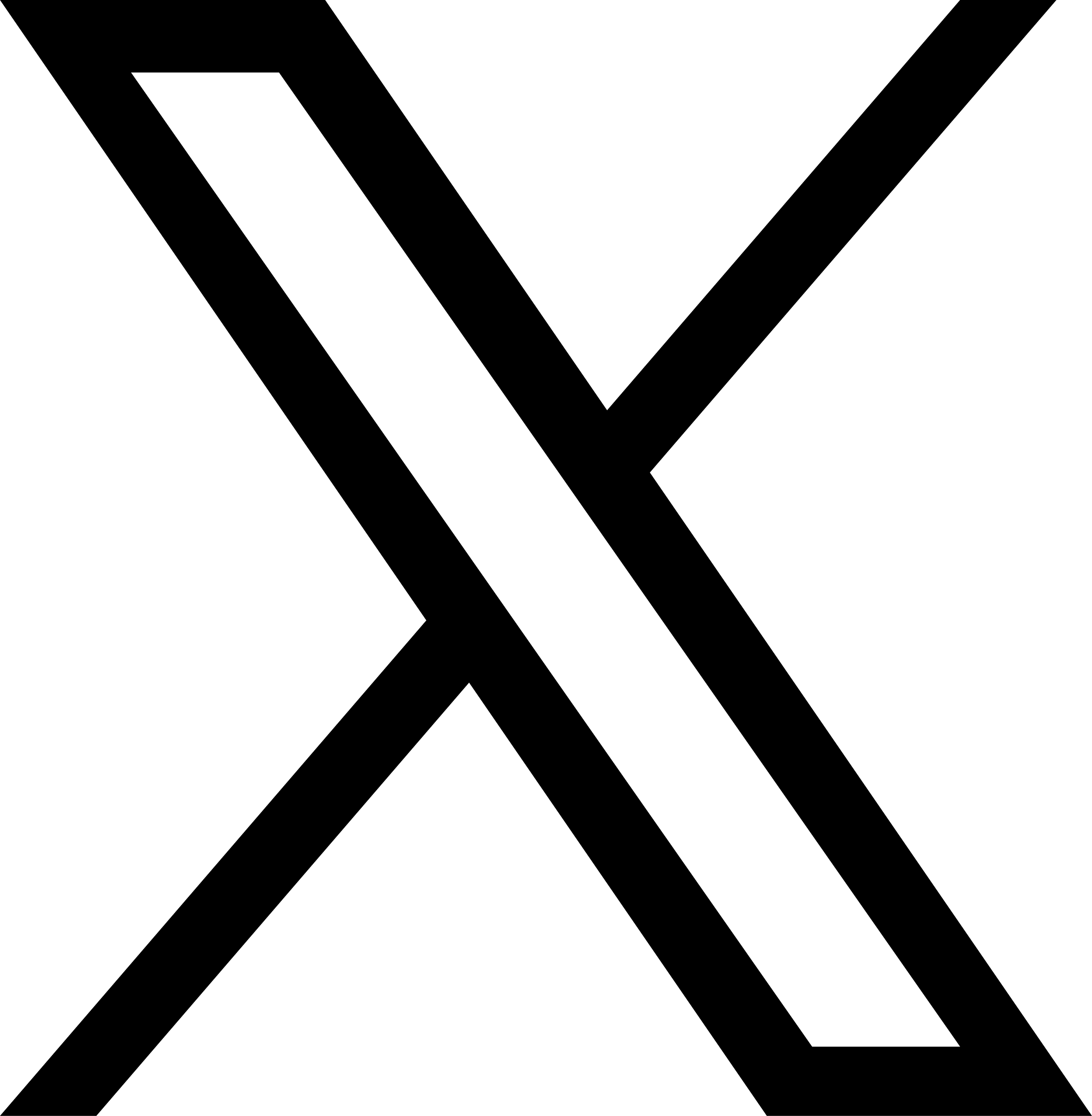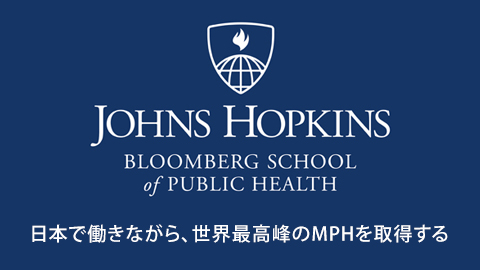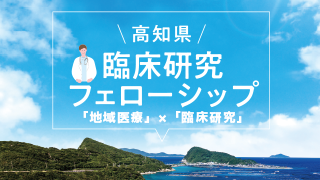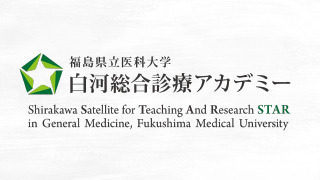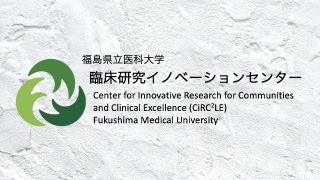新時代の医療をともにデザインする
- 2月号
-
2026February
- 責任編集
- 福原 俊一

学びは、医療者の仕事の中核です
学び続けたい全ての医療者の皆様へ
見て、聴いて、触って、感じて、体験して・・・
さあ、始めよう
- はじめての方
- 会員登録(無料)
Primaria ONLINEは、会員(無料)のご登録でご覧いただけます。医療に関わる公的資格を有する方およびそれを目指す方であれば、どなたでもご登録いただけます。


- インタビュアー:福原俊一
- 京都大学 特任教授
Johns Hopkins大学 客員教授
福島県立医科大学 副学長
- 慶應義塾大学 医学部感染症学教室 教授
- 南宮 湖
グローバルヘルスに興味があり、南インド農村部の病院へ
医学部時代から感染症、特にグローバルヘルスに興味があり、5年生の2学期から1年間休学して南インド農村部の病院へインターンに行った。自分が貢献できることを考えていたが、実際には現地の医療従事者の専門性の高さや熱意に刺激を受け、むしろ多くの学びを得た。卒後は、千葉県の旭中央病院で初期研修を経験。救急外来や病棟で生き生きと働く研修医たちに感銘を受け、医師としての土台が養われた。その後、慶應義塾大学大学院に進み、非結核性抗酸菌(NTM)の疫学研究に取り組む。理論的背景の必要性とグローバルヘルスへの関心から、ジョンズ・ホプキンスのMPHプログラムに第1期生として参加。臨床研究の基礎から実践、幅広い知識を習得したことは、自身の可能性を広げるパスポートとなった。……

- インタビュアー:福原俊一
- 京都大学 特任教授
Johns Hopkins大学 客員教授
福島県立医科大学 副学長
本日は、福島県立医科大学 いわせ総合診療アカデミーの桑原篤憲先生にお話を伺いました。地域医療の最前線で、臨床のみならず研究や行政との連携にも取り組む桑原先生の歩みと、アカデミーの目指す未来についてお届けします。
臨床・研究・地域を繋ぐ「総合診療」の拠点へ
—いわせ総合診療アカデミーの挑戦
私が総合診療医を志したきっかけは、学生時代に見た海外ドラマ『ER緊急救命室』でした。登場人物のマーク・グリーンのように、どんな症例にも対応できる医師になりたいと強く思ったのです。……

03

医療政策を立案し実行する側にいた専門家に、日本の現状や展望をどうとらえているのかを語っていただきます。
カネからヒトへ政策転換を
カネを配れば、問題解決になるのか?
医療法は成立したし、診療報酬や介護報酬もアップしたので、医療・介護関係者は一息ついて新年を迎えることができた。しかし、相変わらず、医療や介護は課題山積だ。……

- 元・内閣官房
社会保障改革担当室長 - 宮島 俊彦
04

研究者としてのキャリアを志す、あなたに最適な学び方を見つけよう。
独立した研究者になるための6つの要件(1.系統的な学習 2.実践的演習 3.データ 4.メンター 5.プロテクテッドタイム 6.仲間)、その一つ一つを先輩たちがどうやって乗り越えて学んでいるのか、具体的な事例を聞いてみましょう。
各種セミナーの紹介・開催告知
今号の「働きながら『研究』を学ぶ」は、充実の3本立てでお届けします。
まずは、臨床医のための臨床研究入門プログラム「臨床研究てらこ屋」をご紹介。2026年6月14日(日)開催予定の第16回プログラムについてもご案内します。続いて、「ジョンズホプキンス大学 School of Public Health MPH 日本プログラム」を特集。プログラムの魅力や内容、説明会情報に加え、3月21日(土)に開催される開講10周年記念シンポジウムの告知も掲載しています。そして最後に、5月17日(日)開催の「第9回 臨床医のアカデミックキャリアの作り方」について、参加概要などをお伝えします。ぜひ、最後までご覧ください!
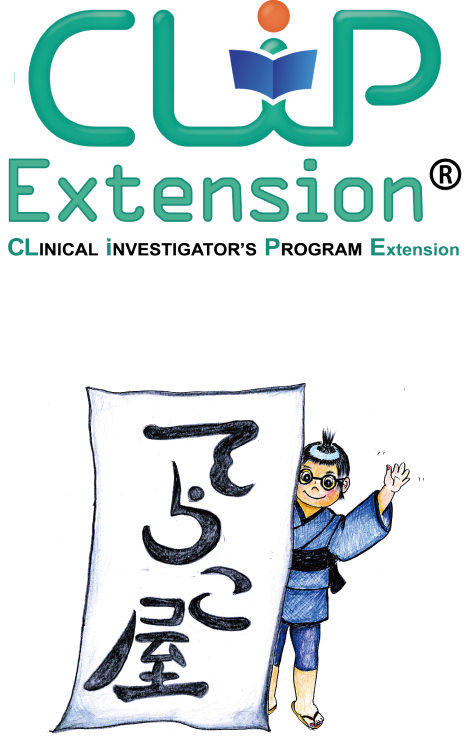
05

第一線の医療者が、臨床研究に取り組み、悩み、紆余曲折を経て、世界に発信した「臨床研究の旅の物語」を読んでみましょう。
あなたが今抱えている、もしくはこれから向き合うことになるかもしれない悩みをうまく乗り越えるためのヒントが、そこにあるかもしれません。
- 研究タイトル
-
日本の研修医における自己申告のベッドサイド研修時間と基本的臨床能力評価試験との関連
リサーチ・クエスチョン(RQ)との出会い・着想の瞬間
リサーチクエスチョンは科研費の申請準備中ふと閃きました。2022年4月に聖マリアンナ医科大学に赴任した際、上司の大平善之先生から科研費の課題提出を勧められました。……

- 片山 皓太 Profile
-
- 聖マリアンナ医科大学
総合診療内科学 助教 - 大阪出身だったが、学生時代に徳田安春先生に出会い、2012年から茨城県の水戸協同病院で総合診療の研鑽を積む。
- 臨床研究も学びたいと臨床研究てらこ屋in福島で福原俊一先生に導かれ、2017年に白河総合診療アカデミーで臨床の傍ら、臨床研究を学ぶ。
- 同時に福島県立医科大学大学院医学研究科 臨床疫学分野に入学し、栗田宜明先生に師事して医学博士を取得。
- 大平善之先生から総合診療科の立ち上げに誘われ、2021年から国際医療福祉大学成田病院に異動し、2022年から現職。
- 聖マリアンナ医科大学